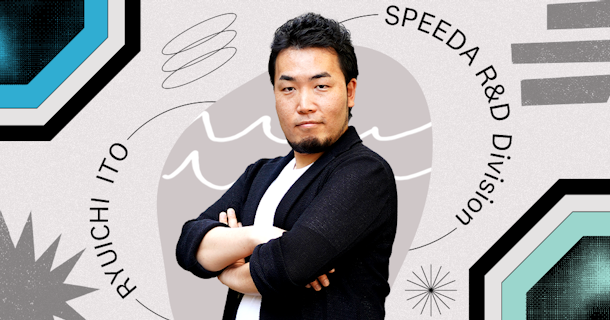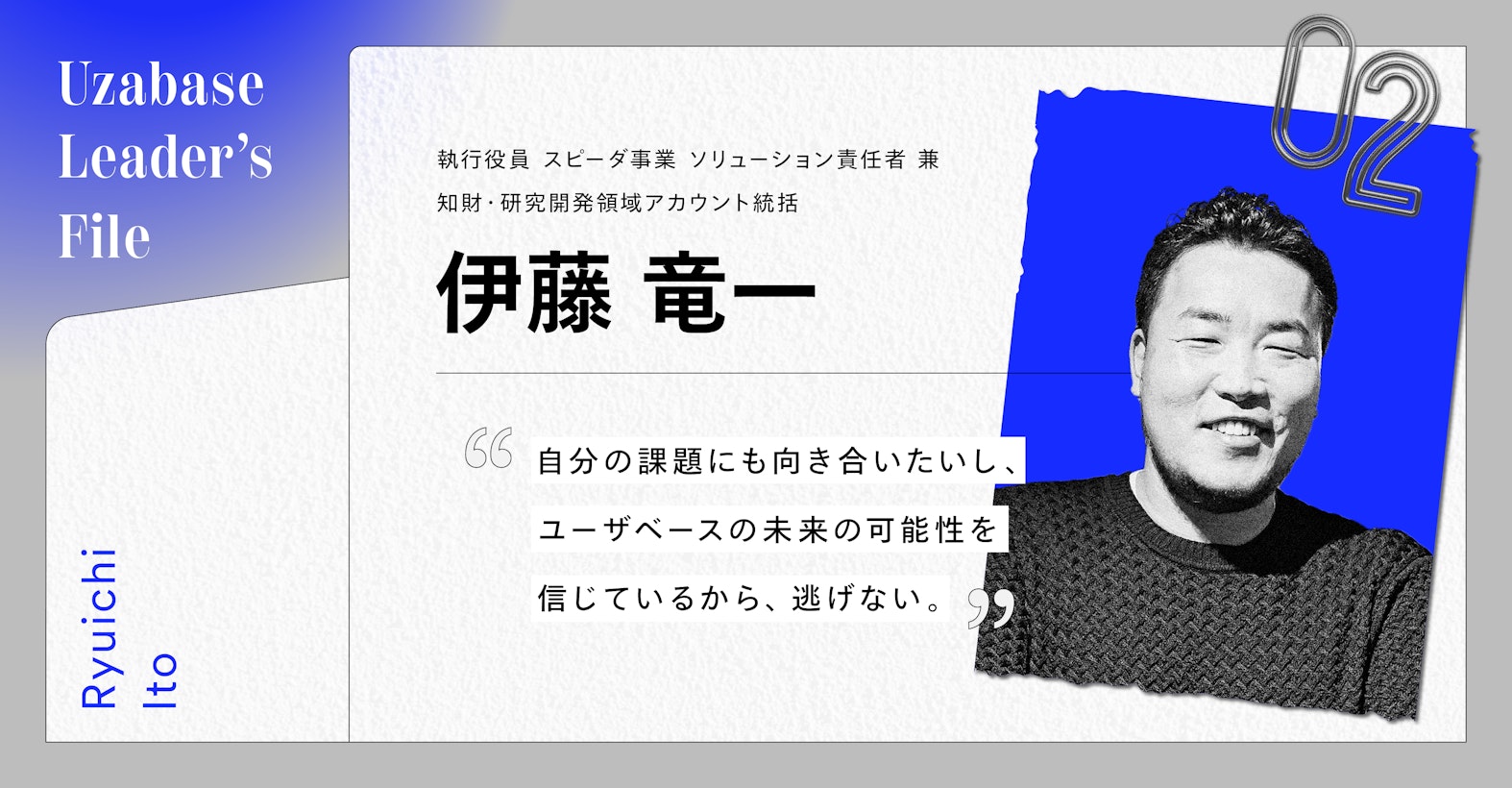顧客起点が軸。新規事業成功の鍵は「現場の解像度を高めること」
そうですね。まだ実効的な影響力拡大はこれからですが、2025年からスピーダ事業のソリューション責任者をしています。たとえば現在ユーザベースでは、エンタープライズ領域における大型取引を指す「Big Deal」を獲得していこうという動きがあります。
ただBig Deal獲得は不確実性が高く、再現が難しい。そこでソリューション部門では、すべてのAccount Executive(以下「AE」※)がBig Deal獲得の機会を最大化できるよう、ユーザベースのアセットを総動員した、複合プロダクトサービスのソリューション提案を構築・型化・AEへの実装支援をすることや、未来の機会とリスクを踏まえ、Big Deal後の定着・拡大に資する3ヵ年プラン等の長期的な取り組みデザイン、顧客価値提供に足りないピースのM&A候補提言や実現後の営業PMIなどを担っています。
Account Executive:顧客企業の総合窓口となり、提案から契約までを担当する営業職
このソリューション責任者に加え、引き続きR&D領域の統括も兼務しています。2024年までは独立した顧客起点組織でしたが、2025年からは営業組織とカスタマーサクセス組織の中にそれぞれR&D領域を担当するチームがあります。僕の役割は、統括としてそれを横断して領域専門性・戦略をアラインしていくことですね。
あらためて、僕の中核は顧客起点にあるんだな、と。R&D領域の市場変革を中心にした「ロマン」を追い求めるだけでなく、スピーダ事業の戦略に即した売上利益の最大化という「そろばん」も考えたうえで、やはり理想の顧客価値を追求し続けていきたいと思っています。
また、その中で、お客様と一緒に大きな仕事を共創し、社会の新たなスタンダードを創っていけると理想ですね。
経済情報群を多角的に活用できるユーザベースの事業アセットの魅力や、「自由主義で行こう」「ユーザーの理想から始める」「異能は才能」といったThe 7 Valuesに紐づく人・風土・環境があるからこそ、役割が変わったとしても、自分の意志や持ち味と、会社の挑戦・成長にシナジーを生み続けられると思います。
さらに、2025年の役割変化によって、入社時からこだわる「ソリューションを通じた顧客価値共創でインパクトを出す」という原点も追求できる体制を築けるのではないかと考えています。

まずは、迷ったらお客様や社外の有識者の声も聞くことですね。
新規事業では、社内で満場一致の賛同が集まることはほぼありません。新規事業であったR&D領域事業は、社内はもちろん、僕自身にも市場専門性はなかったんですが、マーケット創造と顧客価値を追究する気づきや仮説のタネをお客様や社外の有識者にぶつけ、役職者とも対等に近い知識と視座で対話できるレベルまで、仮説の具現化にPDCAを回し続けました。
背中を押してくれたのは、データパートナーやお客様からの「まさにそれを求めている!」という声の広がりでしたね。
次に、結果で示すこと。営業から新規事業を起こすことのメリットは、自分で数字の結果を直接示せることです。約束して、結果で証明して、次の投資を勝ち取って周りの期待や信頼を獲得する。このサイクルを回し続けてきました。
最後に、組織の多様性をうまく活かすことを意識しました。
売上3〜5億円規模の時は、ほぼひとりの発想でも価値と成果を上げ続けられたんですが、10億円を超えてくると組織で役割を分担し、多様な発想を活かしあうことが必須になります。15億円を超えると、今度は自分の創造性を超える新たなアプローチを現場から創発することが成長の必然になる。フェーズに応じて体制も変化させる必要があったんです。
実は立ち上げ当初からです。2019年3月に稲垣さん(稲垣 裕介/ユーザベースCEO)から投資決裁をしてもらったんですが、当時出した資料から何のピボット(事業転換)もなく5年以上にわたって進化し続けています。これは新規事業では珍しいケースだと思います。周囲に理解を得るための社内IR的な動きの方に苦心し続けた立上げ期でしたね。
R&D領域を立ち上げたときから、今なら先行者利益があると思っていましたし、R&D市場自体の価値を拡大できる、人の変革にも貢献できる、これは間違いないなと考えていました。お客様や社外の有識者と対話しながらその確度を上げていったのと、実際に結果が出たことで確信を深めていきました。
企画や事業開発の人が新規事業を立ち上げる場合、現場の解像度があまり高くないことが多いんですよね。でも営業起点だと自分が最前線でセールスをし続けながら、誰よりもお客様と接点を持ち、求められる価値や期待される独自性、お困りごとの相場観や類型化といった、事業の解像度や手触り感を高めていける。
もしも迷いが出たとしても、常に多様なお客様との対話を良いスパイラルに繋げ、自分の理想や社会のあるべき姿への変革を持論とし、言語化をアップデートする。お客様との対話を重ねることで、ブレずにいられるんです。
対話において、お客様が求めることをそのまま事業化するのではなく、「お客様の声に耳を傾けながらも、半歩先の”気づき”を届けて導けるような、創造性のある事業開発をしよう」と意識していました。
あとは、コロナ禍以降「R&Dの事業化・社会実装」実例をテーマの核にした、さまざまなセミナーを主催するなかで、登壇者と高度な対話をしたこともプラスに働きましたね。誰もが知っているような大企業のCxOクラスの方々や、第一線で活躍される現場の方々との50企画を超える対話の積み重ねが、自分の思想の核をつくってくれました。
失敗から学ぶ。リーダーの成長に欠かせない「課題との向き合い方」
2024年2月頃に顕在化したんですが、マネジメントでつまづいたことですね。
R&D領域事業の構想・立上げからずっと、高い理想を掲げ続けてきました。そのなかで、ポジティブ・ネガティブな理由はさまざまありますが、立ち上げ初期を支え、入社2年以上のキャリアを持つ仲間数人の退職が、立て続けに重なってしまったことがあって。最終的にチームに残ったのは、僕のようにキャリアが長いメンバーが数人と、大半は入社1年程度、あるいは1年未満のメンバーだけ。
多様で優秀でポテンシャルの高いリーダーにも挑戦をお願いしつつ、「R&D市場はまだまだ魅力があって伸ばせる。このペースを鈍化させると先行者利益を得続けられないから」と、僕はブレーキをかけず、アクセルを踏み続けてしまったんです。事業としてスピードを落とせない競争環境と、内部の組織成熟度の二律背反の見立て・バランスを見誤り、組織も疲弊させてしまって……。
チームメンバーは30名ほどいたんですが、僕との1on1で聴けている内容と、僕とメンバーの間にいるリーダーたちが相談を受けている内容、さらにリーダーの苦悩そのものの理解にも温度差や差異があり、僕にリアルな本音が上がってこないまま組織内の距離感が広がってしまいました。適切に情報を得る姿勢や寄り添い方、あるいは、リーダー任用や任せ方含め、大規模組織のリーダーの難しさも痛感しました。
それが2024年2〜3月に行った組織サーベイで明るみに出た感じですね。この組織サーベイのあと、稲垣さんと守屋さん(守屋 俊史/スピーダ事業CHRO)がチーム内で問題意識の強いメンバーにヒアリングをして、1つひとつの課題を一緒に改善していくために、半年間伴走してくれました。
実は、フェーズや背景は異なりますが、前職のリクルート時代にも似たような組織マネジメントの失敗経験があって。

前職では3年ほどアドテクノロジー事業という、ほぼ専門性のない領域で新任マネジャーに就任しました。アドテクを活かして、当時知見も多かったHR領域の改革をしたいという想いから、自分で望んでマネジャーになったんです。
でも当時の僕は戦略性が低く、かつ独りよがりなHR領域主語の目線からアドテクを見てばかりいて、アドテクを主な生業にするメンバーとのあいだに軋轢が生まれてしまったんです。「竜さんの戦略は信じられない」「成果も出ない」と言われ、実際に成果を出し続けられず、チームは空中分解してしまいました。
今はあのときと違い、顧客と仲間の声をしっかりとらえた確信ある戦略やビジョンをもって、純粋にR&D領域の市場とお客様にチームで最大限の貢献をし、事業も大きくしたいと思って取り組んでいたつもりでした。
ですが、事業への確信を高め続ける中での情報量・暗黙知の差、つまり、リーダーを含め丁寧な認識共有や形式知化、適切な社内IRが不足したことで、逆に各所との認識ギャップも広がり、未来の期待とリスクの思考が独りよがりになり、大切な仲間との温度差を生み出してしまいました。
本質的に成長しきれていない自分への反省と仲間への申し訳なさがありますね。ただ、改めて自分の個性・特性というか、尖らせるべき強みと補完して助けてもらいたい根源的な弱みも再認識できた機会になったようにも思います。
「目的」と「目標」を分ける。逃げない姿勢を支える信念とは
今年のリーダーの役割は、以前からこの役割を担ってほしいという要望をもらい続けていたものではありますが、期待し続けていただけるのは「逃げないから」ではないでしょうか。
今回のような失敗からは、逃げようと思えば逃げられますし、R&D領域の独立性に固執して、袂を分かつような判断もありえます。でもユーザベースやスピーダという経済情報群のアセットがあるからこそ、僕の事業ソリューション群には意味がある。
また、5年間培ってきた”創業者精神”と言える愛着と価値実感を、もっとみんなと分かち合いたい。だから自分の課題にも向き合いたいし、ユーザベースの未来の可能性を信じているから、逃げない。まだまだユーザベースの中で突き詰めたいことがたくさんある。
そういう姿勢を見て、「いざ急場になっても共に経営の屋台骨を支える仲間である」と思ってもらっているのではないかと。
そうですね。でもユーザベースのカルチャーとして、相手に辛辣なことを言わなければいけないときは、伝える前に必ず相手がその言葉を受け止められる心の状態をつくってくれますよね。
あと、これは僕の考え方なんですが、何か理想を掲げるときは、その理想を「目的」と定義して、そこに向かう手段として「目標」を置くんです。僕がメンタルを維持できるのは、この「目的」が明確だからだと考えています。
「いま問題とされているのは『目標』の部分であって、『目的』に到達するためならその指摘にも耐えられる、順応できる、自分を矛盾なく変えられる」という発想ですね。
もしも「目的」がイコール「目標」、あるいは短期的なもので、それひとつの成否で一喜一憂するようなものだったら、目標が問題視された時にメンタルが耐えられないと思います。でも自分にとって目標は、目的に到達するために乗り越えるべき「壁」なんですよね。
さらには「禍福は糾える縄の如し」という達観の精神もキャリア経験の中で磨かれました。

「未来へのバトンをつなぐ人」ですね。投資家からの期待や現場の1人ひとりのWILLがあって、それを各階層のリーダーたちがいい形でバトンをつないでいかないとリレーにならないですよね。もちろん、未来への事業の発展・持続成長をつなぐこともバトンリレーです。
リーダーは芯がしっかりしていないといけないと思っています。
会社から求められることだけを実現するのはマネージャー。リーダーは、自分のキャリアやライフワークで実現したいことを描き、自分がユーザベースにいる意義とつなげてWILL(意志・やりたいこと)を描き、進化させ続けられる人だと思っています。
僕もユーザベースでずっとR&D領域のありたい姿を掲げてきて、最近はBig Dealの価値と持続性を高めることにもWILLを感じています。最終的な目的として、人と組織の変革やその起点に貢献するようなことを定義しており、自分の芯がはっきりしています。
ユーザベースにおける社内起業のいいところは、ユーザベースの組織力や経済情報群という多角的な事業アセットが使える点。そのアセットを使える希有な環境と立場でさまざまな挑戦を描けるからこそ、リーダーは自分の芯を持ち、それをうまく会社と自事業・組織、さらに自身の成長につなげていく必要があると考えています。
挫折してもまた挑戦できる。ユーザベースが育むリーダーシップの土壌
「何があってもリカバリーはできるんだ」という精神ですね。自分の理想を叶える道程では、思い通りにいかないこともたくさんあるはず。でも何度でもリカバリーできるし、ユーザベースという会社は、逃げずにそこに真剣に挑んでいる人を必ず助けてくれるし守ってくれます。
僕は単純な傾聴や寄り添いのマネジメントが苦手なので、まずは自分の芯の見つけ方をサポートします。いまリーダーとして進化し続けられている人たちは、目の前のことに全力で向き合いながら、市場や組織の変化に良い意味での違和感を持って自分が貢献するべき芯を定義し、個性・持ち味・エッジを輝かせてきた人たちだと思います。
ただ、基本は止まらない実行力が重要です。日々仕事をしていれば多方面からノイズも入りますが、とにかく今に集中する。そのうえで、世の中の流れや社内の変化をとらえ、それをもとに四半期などの自律的なゴールセッティングを実行していく中で、芯となるテーマを見つけ、共存させていく。その行動と思考が基盤です。
そして、その先に自分がどうありたいかを描くこと。たとえば「リーダーになる」「役員になる」も手段なんですよね。大切なのは「リーダー・役員になって何がしたいのか」。やりたいことの芯が明確で、それを信じられる仲間が集い、強い組織や事業が育つ。これが持続性を生みますし、そうした芯=目的が明確になれば、そこに行き着くまでの手段=目標の段階で逃げることは問題ないとも伝えたいと思っています。

あとは、僕はユーザベースに入社して9年半とキャリアが長い方なので、社内にはそれなりの人脈があります。入社歴の浅いメンバーが悩んでいたら、その人の悩みに応えられそうな人をつなぐことができる。そうした挫折を乗り越えるキッカケづくりをしながら、メンバーの今の目標設計・達成や未来の目的創造を応援していきたいですね。
次世代の経営層育成。自分の芯を持ちユーザベースの未来を描く
2024年までの役割は組織マネジメントと事業開発が、切っても切り離せない関係にありました。組織サーベイを通じて顕在化した組織の問題にほぼ1年トコトン向き合ってきたのが2024年だったと思っています。その分、事業の次なる発展・戦略について考える余力は以前よりだいぶ減っていました。それでも自分の好きな「顧客接点」は欠かさずリソースを割いてきたつもりです。
そんななか、R&D領域の体験・実感からBig Dealのつくり方を磨き込んできて、ようやく型化できそうなシナリオが見えてきたんです。2025年はこれを大企業アカウント統括本部と共にチューニングして、他領域への応用展開やシナジーも見据えながら、新組織として横串の価値を探究しようとしています。
かつ、2025年は直接のマネジメント対象者が3分の1に減ったので、組織マネジメントとうまく両立しながら、横串の価値を追求し、大企業アカウント統括本部を中心としたユーザベースのケイパビリティ(組織や個人が持つ能力や潜在力)の向上や、スピーダ事業としての未来の勝ち筋の具現化・実装に貢献したいですね。
この事業貢献で短期の成果や存在価値を見いだしつつ、中長期には変わらぬ情熱の対象であるR&D領域の再成長に対する仕込みや、元のケイパビリティを活かせる組織人材開発領域などにも邁進・自己投資していこうと考えています。
そうですね。Big Deal推進にも、R&D領域の未来をつくり直す取り組みにも、新領域探索にも十分リソースが割けるはずなので、短期の成果・長期の仕込をバランスしながら、広義にR&D関連領域や管掌範囲で、スピーダ事業に売上100億円規模の未来インパクトをつくれる土台を築きたいですね。
先ほどの質問にもあった「リーダーとは? リーダーを育成するには?」という問いをみんなに聞いてみたいですね。
ユーザベースにはいろいろなリーダーがいて、それぞれ横比較しづらい価値をもっています。僕はセールスに軸足を置きつつ、自分の領域事業軸で、マーケティング、ブランディング、プロダクトマネジメント、事業開発、パートナー探索、EBITDA(※)ベースの事業計画策定・達成コミットなど、多様な経験をさせていただきました。
実地経験の積み重ねと節目にいただく問いを起点に、自ら機会をつくり出し、機会によって自らを変えることで、リーダーとしての幅広い成長をさせていただきました。他のリーダーは自分がリーダーたる経験や期待役割をどう高めてきたのか、どう高めてもらえてきたのか?、いろいろなケースを知りたいですね。
EBITDA:企業の収益力を示す指標のひとつ。Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization/利払前・税引前・償却前利益を指す
ここまで僕たちに投資してくれ、変わらず期待もし続けてくれるユーザベースに深い恩義もあるので、ひとりでも多くリーダーを育てることに、さまざまな側面から貢献していきたいですね。
未来にバトンをつなぐためにも、リーダーになりたい人材を顕在化させるとともに、次世代の経営層を育てる環境を整える必要があると思っていますので、2025年4月からは社内のリーダーズアカデミーのひとつの講座の企画と講師も務め、多様なリーダーと新たに交流しながら、自らの貢献幅・多様性も広げていきます。

編集後記
竜さん(伊藤のあだ名)に単独インタビューしたのは約3年ぶりでしたが、一貫してR&D領域に集中し続けていて、改めてすごいなと思いました。今回はマネジメントにおける失敗経験について話してくれましたが、本文にもある「何があってもリカバリーはできるんだ」という強い言葉には、私自身も励まされた気持ちです。周囲からは強い人だと見られがちなリーダーでも、手痛い失敗をしたこともある。そんな泥臭い姿もこのシリーズでは紐解いていきたいと考えています!